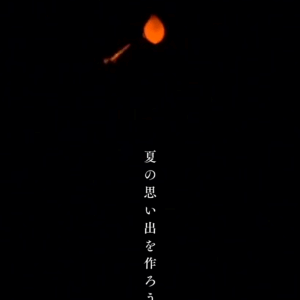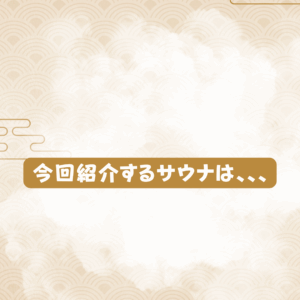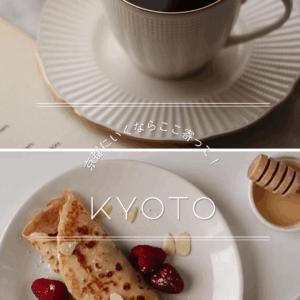ふと立ち止まった電柱、通勤中に何気なく目に入ったポスター、駅ナカの落書きのような貼り紙…。
「これ、広告だったんだ」と後から気づくような、“広告っぽくない広告”がいま注目を集めています。
いかにも広告という見た目では、情報があふれる現代ではスルーされがち。
だからこそ、あえて“らしくない”形で潜り込む広告手法が、逆に人の心をつかむのです。
■ たとえば、こんな“広告っぽくない広告”
手書き風ポスター
→「◯◯で人生変わった。信じるか信じないかはあなた次第。」
思わず調べたくなる仕掛けに。
電柱の小さな貼り紙
→「この道の先、10分で異世界体験できます」
実は地方観光施設への誘導広告だったりします。
街頭アート風の壁面
→ アーティストの作品と思いきや、最後にブランドロゴが小さく入っている
落書き風のステッカー
→ インスタにアップした人にだけプレゼントキャンペーンを仕掛けている
■ なぜ“広告らしくない”のが効くのか?
「情報」ではなく「違和感」で引きつける
→ 一瞬でスルーされる時代、違和感が武器になる
共感を生む「遊び心」
→ 余白のある表現が想像力をかき立てる
SNS時代に強い
→ 「これ広告なの?」と思ったものほど、写真を撮ってシェアしたくなる
■ 実際の活用事例
都会の路地裏に「貼ってはがせる謎ステッカー」を大量設置 → 話題化してZ世代が自主拡散
商店街のシャッターアートにQRコード → 読み込むと地元ECサイトへ
公園のベンチに貼られた“人生相談”風のメッセージ → 実はメンタル系サービスの広告
広告というより、「しかけ」や「ゲーム」として楽しんでもらう設計がカギになります。
■ 広告は“見せる”から“気づかせる”へ
広告らしい見た目を捨てた瞬間、広告はもっと自由になります。
「この広告、面白いな」ではなく
「これ広告だったの!?」という驚きと共に記憶される。
そんな仕掛けが、次の集客の形をつくっています。
広告に“正解”はありません。
でも、“気づかれたら勝ち”という時代だからこそ、
広告らしくない広告の出番が増えているのです。